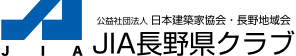時空へ
2012年08月11日
「時空へ」(2012.08.11) 西沢利一(西沢建築研究所)
近代美術館で、昨年末から今年の始めにかけて開かれた、ヴァレリオ・オルジャティ展のカタログを友人からもらった。そう言えば、オルジャティは篠原一男のファンだった。
篠原の作品<詩人、谷川俊太郎の住宅>の土の斜面の部屋には、当時ガツンときた。そこで詩人はハンモックを吊っていた。この作品の篠原の文に、「柱も壁も筋違にも、ただそれだけの機能を表示する即物的な事物の集合で空間を組み立てられないか、架構要素に、あるいは空間の輪郭に込められてきた、さまざまな意味を、もし可能ならば思い切って消してしまいたい」・・・30年以上前にすでに考えていた。
オルジャティだが、プランタホフ農学校の講堂などはまさに篠原の直角三角柱の家<プリズムハウス>だ。個人的にはフリムスのアトリエが好きだが、この人のシンプルさには、いろいろ仕掛けがある。スイス連邦工科大学ローザンヌ校のラーニングセンターなどは、SANAAのものとは別の、ラーメンバランスをわざと崩しながらバランスを感じるという奇妙な存在感がある。また、実現しなかったが、ロシアのペルミ21世紀美術館はこの世のものとは思えない。この辺は篠原にはない静かな土着性を感じる。
オルジャティと篠原は、すっきりとした単純彫刻的な形を好むが、まわりとは決してつながらない孤高さと美しさがある。そこに至る一端が篠原の文章から探れる。
<・・・見えない遠くに、見知らぬ美しい街を思い・・・>
<・・・時間が空間の中に、すっかり吸収されてしまっていた。この光景は現象しなければいけない。>
<モダニストは、果てのない時空で美しい生成と消滅を繰り返すこの世界都市には対応できない。>
時空感覚なのだ。言葉からは想像できても、実際この感覚はわかりにくいが何となく納得できる。たぶん、一度見たり経験したものを自分の感性の中で昇華、構想している。篠原は好きな思想家、ジル・ドゥルーズを置換引用している。
「住宅建築を機械と見なすということは、意味の問題が後退しているということである・・・
住宅はそれ以前にまず、意味の空間であることを設定して・・・そこから意味そのものの内容ではなく意味を生産する機械装置であることへ前進していく・・・」
(意味を時空感覚と読みかえるとわかりやすい)<住宅は芸術である>から始まる私のコンセプト系は意味空間としての住宅の提起であった・・・」
時空とはもちろん時間と空間の集合体?と考えられるが、空間とはがらんどうで中身のない状態を思い浮かべる、そこに時間が埋め込まれないとただの思い込みになる。この時間をどう考えるかで空間と呼ばれる意味が表出してくる。
篠原は<時間を吸収した空間>と呼んでいるが、住宅であれば(家族の時間)が空間に吸収される。家族について、ドゥルーズの影響を受けた浅田彰が「逃走論」のなかで、(家族が病んでいる)と書いているが(家族のあるべき姿)という言葉に疑問を投げかけている。
国のスローガンやメディアの洗脳で、イメージ的に大変無理を抱え込んでしまった。この時代は(家族という病)のひきおこした末期症状ではないかと考えている。この辺りは、TVドラマや住宅メーカーの広告を見ていると、何か違和感を覚えることで何となくわかるし、ジワジワと染みてくる無自覚が恐い。(家族の時間)とはそんなに美しい額縁でなく毎日の反復のことだろう。
ところでこの広告だが、広告とはあくまでも他の商品と比較する(差異化)であるが、ある意味では選択肢を増やすことである。そのもくろみは、より多く売ろうという量的発想が背後に見え隠れする。そして選ぶ方の嗜好がコロコロ変わる気まぐれさを、同時に受け取る。
磯崎新は(クライアントは芸術家にも、勿論建築家にも同様に他者である。それは横暴であると最初から決まっている。他者は横暴なものだから。建築家は最初から溺死体になっていると思う方がいい。もがけばもがくほど、悪趣味の側に引き寄せられるというメカニズムは厳然と作動している。)といい、なかば突き放しながら<他者としての建築家>と言い切った。磯崎は建築を「霧のように立ち込めている虚体」もっと言うと「見えない都市」として出発し、浅田彰や柄谷行人といった若い人達にもまれながら、消費時代に幻滅をし「廃墟論」を確立していく。磯崎の建築で内部空間をうんぬんするのはあまり意味をなさない。昆虫が固い外皮をまとっていて、死んで内部がなくなっても外皮だけがかろうじて残るように、磯崎は<廃墟として残るモノ>を目ざしているのだから。
建築家として一番言葉を多く持っている磯崎の作品をシルエットとして見るとよくわかる、何となく憂愁が漂っているのを感じる。
磯崎と違って、篠原やオルジャティは同じ時間軸でもまだあきらめていない。スイスに生まれ育ったオルジャティは、都市カオスにはあまりなじまないが、東京が舞台の篠原にとって幾何的ベースの手法では大変苦しいものになっていった。世界の都市を旅するうちに、おぼろげながら空間量になじんでいったがまだ悩んでいた。そこで出会ったのが、レヴィ・ストロースの「野生の思考」である。あるものはあるとしての野生で、心の解放である。ここから<野生の機械>という概念を生むことになる。「上原通りの住宅」からの一連の都市住居はここからの出発である。PS平山氏の「未完の家」もこの系列に入る。しかし「孤独は雑踏のなかにある」と言った哲学者三木清の言葉に魅せられた篠原の本質は変わらない。こんな時でも美しい時間を夢想する。ジョセフ・コーネルの「箱の中のユートピア」の様に、非現実を現実にする力を信じている。
篠原やオルジャティの仕事を想うとき、精神的に背すじが伸びる。時空感覚を思い浮かべることで、茫洋とではあるが人間が生きるための空間<建築は芸術である>ことを再び期待させる。