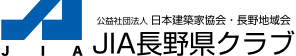【第3回JIA長野建築賞2024】審査講評
2025年02月25日
第3回JIA長野建築賞2024 審査講評
主催:公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部長野地域会
審査員:山本理顕氏、日野雅司氏、川口有子氏、仲 俊治氏、玉田 誠氏
応募総数:46点
【審査講評】山本理顕
「軽井沢の居場所・遠藤隆洋」が大賞である。明らかに他の案を圧して美しい建築だった。
玄関ドアを開けて「通り土間」から見る「居間」の佇まいがとても穏やかなのは、白く塗られた石膏ボードの壁が 構造用合板の天井材から切り離されて、家形が自立しているように見えるからである。その家形はずっと奥まで続いて、その家形の中に4世帯14人の家族のための3つの部屋が並んでいる。左右の長い濡れ縁に挟まれるような、その平面構成が鮮やか。斜面に沿って床が少しずつ上がって行くが切妻屋根は水平が保たれている。その水平に保たれた大きな屋根が森の中に穏やかに収まっている。この遠藤さんの建築に対立的だったのが「商店街の小さな保育 園・土用下淳也、山本純平、福井竜馬」である。駒ヶ根市の商店街に建つ保育園の計画だが、計画者は公益社団法人のJOCAである。JOCAは2018年にその本部組織を東京から、この駒ヶ根の「銀座商店街」に移したのである。そのJOCAか経営母体となる保育園で、JOCAは近くに本部ビル、健康増進施設もつくっている。健康増進施設というのは会員制スポーツセンターである。保育園はとてもよくできている。外に対してできるだけオープンにしようとする意図がよく分かるのである。でも、それはJOCAの思想である。この商店街に於けるJOCAの立場はディベロッパー的である。JOKAはディベロッパーとしての役割を担うのではなく、「銀座商店街」と呼ばれるこのコミュニティーの人びとの利益をどこに求めるか、という視点が必要だったのではないか。商店街全体として、どのような利益を得ることができるかという視点である。その時にこの保育園はどのような役割を果たすのか。商店街の人びとやそこに買い物にくる地域社会の人びとと共にある保育園というのはどのような保育園なのだろう。
設計者の土用下さん、山本さん、福井さんの思想はこのディベロッパー的なJOKA思想とどう関係しているのだろう。それが見えにくいのである。
審査は「軽井沢の居場所」と「商店街の小さな保育園」の評価によって拮抗したが、最後は、設計者の主体性という観点から、遠藤さんの建築が大賞に選はれた。
日野雅司
46作品という多くのご応募をいただきましたが、まずは豊かな立地条件を上手く生かした建築がとても多い印象がありました。一つ一つは小さな建築たちですが、非常に普遍性・プロトタイプ性の高い提案が集まったことにも驚きました。これは長野における自然環境・地域環境というものが、シンプルに原初的な建築条件を提示し、それに対して設計者たちが真摯に答えていることが理由なのではないかと思います。建築をつくる環境に向き合って素直に答えることの大切さ、設計者として長野で建築を作ることの魅力を改めて感じることができ、私としてもとても良い経験となりました。
そのため応募案はどれもすばらしく、優劣をつけることが非常に難しいと感じられましたが、その中でも「環境への対応」について新しい提案性に富む数点を一次審査では選ばせていただきました。どれも建築の未来を切り開くような、アイデアを持った作品たちを賞に選出することができ、充実した審査だったと思います。
川口有子
応募作全体として、都市から移住した方の住宅が非常に多くありました。コロナ禍を経て、リモートワーク・2拠点居住など人々の暮らしが変わってきたことは周知の事実ですが、長野においては、その暮らしが、必ず屋外の自然環境と結びついて提案されていることが、大変すばらしいと感じました。
私が現地に伺った長野市~軽井沢の4作品は、若い建築家の処女作か、またはそれに近い作品であったことから前述した背景の中で何を感じ、何にチャレンジするかという意識が比較的明確に表れていると感じました。公開審査では、その問題意識があるか、共感を得られているか、ということが議論されました。審査する側がむしろ問われているという緊張感もあり、こうした議論ができたことは大変な収穫でした。候補者・施主の皆様、運営に尽力された事務局の皆様に感謝いたします。
仲俊治
2024年の第3回JIA長野建築賞には46作品の応募があった。応募資料に基づく1次審査で7作品が選出され、2次審査(現地審査)に進んだ。2次審査は10月下旬の2日間にわたって行われ、7作品全てが大賞候補であると確認し、11月25日の公開プレゼンテーションおよび公開審査にて、大賞を決定した。
大賞候補の7作品に残ったのは、戸建住宅、別荘、賃貸住宅、住宅を含む複合建築、保育園とさまざまであり、うち改修は3作であった。大賞をめぐる議論は、個別のテーマの確認から始まって次第に、周辺との関係性や共感可能性といった議論に発展した。特に「軽井沢の居場所」と「商店街の小さな保育園」の間で交わされた議論は、社会に対して美しい空間が提案されているかという内容といえよう。最終的には、家族の来歴や特徴的な地形に応答しながら、新しい空間をディテールと共に提示した「軽井沢の居場所」が大賞として選ばれた。
玉田誠
学びの多い建築賞であった。1次審査では長野の気候や地域性に応えた多様な46作品の建築が集まった。その中でも広く建築や社会全体の問題に繋がる可能性を持った7作品が現地審査に選ばれた。最終審査ではその思想や未来への考えについて質疑や議論が行われ、審査員投票によって遠藤隆洋の「軽井沢の居場所」、香川翔勲の「縫合する建築」、土用下淳也、山本純平、福井竜馬の「商店街の小さな保育園」で票が割れることになった。特に遠藤氏の軽井沢の環境に反応してできた完成度の高い建築か、土用下氏の制度でがんじがらめの福祉施設(保育園)を地域に開く提案のどちらを選ぶかで議論が白熱し、建築家の思想がどのように建築空間に現れているのか、という点で最優秀賞に「軽井沢の居場所」が選ばれた。審査全体を通して今回が単なる賞の選考会ではなく、様々な角度から建築について考え、それがどのように物化されているのか、ということを審査員だけでなく参加した全員で考え・学ぶような貴重な場であったと思う。
【大賞】
建物名「軽井沢の居場所」
設計者:遠藤隆洋(一級建築士事務所 遠藤隆洋建築設計事務所)


【優秀賞】(応募番号順)
建物名「松本三の丸スクエア」
設計者:岩岡竜夫(東京理科大学)、森 昌樹(MORIIS Atelier)、横尾 真(OUVI)
「松本三の丸スクエア」は松本城の敷地に隣接する道路の拡幅をきっかけとして新築された住宅、診療所、私設美術館のコンプレックスです。それぞれの機能により中庭を緩やかに囲い取ることで、個人の領域ながら地域と共有する場をつくることに成功しています。審査会では中庭に対してどれくらい建築が開放的に構えるべきか、ということが論点となりましたが、それはもう少し時間をかけて議論できれば、と口惜しさも残っています。端正で合理的な構造形式も含め、城下町松本ならではの品位を感じる建築であり、これからの都市居住の模範となる提案だと感じました。(日野雅司)


建物名「ORCHARD」
設計者:納谷 新、太田 諭(/360°)
「ORCHARD」は、飯田市の賃貸戸建て住宅群の改修計画です。住戸を間引きながら空地を設け、1つの敷地に中に6棟の住宅とシェアキッチンを設けたもった共用棟が点在する計画となっています。おそらくは地方都市として珍しいプログラムであると共に、大きなランドスケープに建築がばらまかれたような新鮮な風景が実現しています。戸建て住宅のコモンスペースを考える上で重要なプロジェクトであり、審査においてもそこを住民やオーナーがどのように使いこなしていけるか、が論点になりました。共用棟ではオーナーがカフェを運営する予定とのこと、今後の活動が期待されます。(日野雅司)


建物名「縫合する家」
設計者:香川翔勲(株式会社トベアーキテクト)
様々な時代や価値観を重ねて増改築を繰り返した住宅を新しい時代に向けた建築に更新する計画である。異なる時代に作られた柱同士を貫で柔らかく一体化することで、全体の構造を縫合し、空間や環境をつなぎ合わせるというアイディアの新しさが評価された。貫による構造の縫合については、その効果や法解釈、ディテールなどの様々な点で検討・議論の余地が多く残っていることは確かである。しかしながら、今にも壊れそうな寄せ集めの建築を、貫を使ってひと束にまとめ上げるという、その考え自体が概念として非常に説得力があり、建築の新しい局面を予感するものであった。(玉田 誠)


建物名「中山山荘」
設計者:霜鳥聡志(株式会社霜鳥聡志建築設計事務所)
驚くほど開放的で、1次審査では住宅性能やプライバシーに無頓着ではないか、という疑問をもちました。しかし、現地で伺うと、ローコストで最大の面積を確保しながら、森に囲まれた暮らしをしたいという施主の理想に、創意をもって答えたものであるとわかりました。2×8材を並べた1枚屋根の架構や、サッシだけで構成された外装など、建築の構成部材がすべて目に見え、アウトドアビジネスに携わる現オーナーが今後手を加えることもできそうです。例えばお店のように地域に開けば、さらに魅力的な建築になると感じました。(川口有子)


建物名「商店街の小さな保育園」
設計者:土用下淳也、山本純平、福井竜馬(株式会社kyma)
地方都市の商店街に計画された保育園である。子どもが駆け回る空間を内外に連続させるかたちで、商店街からよく見える位置につくりだした点が目を引く。ここには、上下足の履き替えラインの設定や建具の作り方など、周到な配慮が潜んでいる。商店街沿いに他の関連施設があり、連携した活動も行われている。このように、建築空間を基点として、多世代が共に生きる風景を街角につくり出した点が高く評価された。点と点を繋いで商店街全体に活気を与えるこのような手法は、他の地域でも参考になると思われる。ぜひ、活動を継続してほしい。(仲 俊治)


建物名「軽井沢の座標」
設計者:櫻井雄大、中村亮太、中園幸佑(株式会社アトリエ・トルカ)
とても美しいドローイングが1次審査で話題となりました。樹木と既存建築の柱が並ぶ分布の中に、コンクリートで新しい点をつくり、施主や場所の記憶を次世代につなぐというリノベーションです。コンクリートのキッチンや階段は、簡素ですが、慣習的でなく、とても慎重にデザインされています。また、敷地に塀がなく、どこまでも続いているような雑木林で、その中にふとこの建築が現れるような印象がありました。時間や空間の広がりそのものを、デザインの対象としようとする野心的なプロジェクトです。(川口有子)